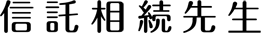生命保険や不動産活用は相続税対策になる?その他の節税策と注意点
- 公開日:
- 更新日:
相続税の負担を軽くする方法には、生命保険の活用や不動産への資産組み換えなど様々な選択肢があります。それぞれの対策の仕組みやメリットだけでなく、注意すべきポイントもしっかり押さえておくことが大切です。ここでは、50代の子世代の方向けに、親の相続に備える主な相続税対策とその注意点をわかりやすく解説します。
生命保険を活用した相続税対策
生命保険は相続税対策としてよく活用されます。その理由は、生命保険金には相続税法上の非課税枠が設けられており、相続人(法定相続人)が受け取る死亡保険金の一部が非課税になるからです。さらに、契約形態を工夫することで所得税の非課税枠を利用し、相続税負担を軽減できる場合もあります。以下、生命保険を使った具体的な節税ポイントを見ていきましょう。
死亡保険金の非課税枠(法定相続人1人あたり500万円)の活用
被相続人(亡くなった方)が生命保険に加入しており、相続人が死亡保険金を受け取った場合には、「500万円 × 法定相続人の数」まで相続税が非課税になる仕組みがあります。この非課税枠は、相続人全体で受け取った保険金に対して適用され、たとえば法定相続人が配偶者と子2人の合計3人なら最大1,500万円までの死亡保険金が相続税の課税対象から除かれます。受取人が相続人でない場合(例:孫が受け取るなど)はこの非課税枠は使えませんので注意が必要です。
具体例:法定相続人が子ども2人の場合
非課税枠は500万円×2人=1,000万円となります。このケースで死亡保険金800万円を子ども達が受け取った場合、1,000万円の枠内に収まるため全額が非課税になります。一方、現金で800万円を遺した場合は基礎控除枠を超えればその全額が課税対象となる可能性があります。生命保険金は受取人固有の財産として遺産分割協議の対象外で直接受け取れるため、迅速に葬儀費用や納税資金に充てられる点でも有用です。
保険料の負担者を工夫して所得税非課税枠も活用
生命保険金に係る税金は、「誰が保険料を負担したか」と「誰が受取人か」によって課税方式が変わることをご存知でしょうか。典型的な契約では、被相続人自身が保険料を支払い、相続人が死亡保険金を受け取るため相続税が課税されます。しかし、保険料負担者と受取人を同一人物(相続人本人など)にする契約形態にすれば、死亡保険金は相続税ではなく所得税(一時所得)の対象となります。一時所得には年間50万円の特別控除があり、さらに課税対象額はその利益部分の1/2だけです。結果として、相続税課税の場合よりも低い税負担で済むケースがあります。
具体例:子どもが契約者(保険料負担者)となり、親を被保険者・子どもを受取人とする保険に加入したケースを考えます。
仮に子どもが支払った保険料総額が500万円、死亡保険金が1,000万円だった場合、所得税の計算上は受取額1,000万円-支払保険料500万円-特別控除50万円=450万円が一時所得となります。
その1/2の225万円が課税対象となり、受取額全体に相続税がかかる場合と比べて大幅に負担を抑えられます。この方法では死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人)は使えなくなるものの、所得税の特別控除を活用する形で節税効果が得られるわけです。ただし、この契約形態では子ども自身が保険料を払い続ける必要がある点や、契約内容によっては贈与とみなされるリスクもあるため、事前に専門家へ相談して適切な契約設計を行いましょう。
不動産の活用による相続税対策
現金・預金などのまま遺産を残すより、不動産を活用することで相続税評価額を下げられる場合があります。これは、不動産の相続税評価額(課税評価額)は市場価格に比べて低く算定されることが多いためです。さらに、賃貸用の不動産にすれば利用や処分に制限がかかる分、評価額が一層引き下げられる特例もあります。ここでは、現金を不動産に組み換える方法や賃貸物件・小規模宅地等の特例を活用した評価減について、具体例を交えて説明します。
評価額の低い不動産への資産組み換え(現金→不動産)
現金は額面どおり100%の評価となりますが、不動産は路線価や固定資産税評価額に基づいて評価されるため、市場価格より低い評価額になるケースが一般的です。そのため、生前に現金・預金を使って不動産を取得したり建築したりすることで、相続税の計算上の財産評価額を圧縮できる可能性があります。
具体例:現金1億円を都市部の土地に組み換えた場合
その土地の相続税評価額は「路線価×地積」で計算され、路線価は公示価格の80%程度が目安となります。つまり、1億円相当の土地でも評価額は約8,000万円に抑えられる計算です。さらに1億円で建物(賃貸マンション等)を建築した場合、建物の評価額は固定資産税評価額となり、建築費のおよそ60%程度(約6,000万円)になることもあります。結果として、1億円の現金を土地に変えれば評価額8,000万円ほどに、建物に変えれば約6,000万円に圧縮できるわけです。老朽化したアパート等を建て替えて新築不動産にするケースでも、建物評価額は建築費ベースの算定となるため、現金を投下した金額より低く評価される効果が期待できます。ただし、不動産取得にはコストがかかり、相続後に売却しにくい(流動性が低い)点もあるため、この後述べる注意点に留意しましょう。
賃貸物件や小規模宅地特例の活用で評価減を図る
不動産を賃貸用として活用すると、さらに相続税評価額を下げることができます。賃貸物件では、土地については「貸家建付地(かしやたてつけち)」評価が適用され、一般に更地評価より約2割減額(評価額の約8掛け)されます。建物についても「貸家(かしや)評価」として評価額が3割減額されます(自用の建物と比べて賃借人がいる分だけ価値が低いとみなされるため)。例えば、1億円で新築した賃貸アパートの場合、上記の土地・建物の減額を反映すると相続税評価額が約4,200万円になるケースもあります。実際に税理士の試算でも、借入を活用して賃貸アパートを建築したことで正味の財産(課税対象額)が約6割減少した例が報告されています。
また、被相続人が住んでいた自宅の土地や事業用・貸付用の土地については、「小規模宅地等の特例」を適用することで大幅な評価減が可能です。たとえば、同居の親族が引き継ぐ自宅の宅地であれば330㎡まで80%減額、貸付事業(賃貸)の宅地であれば200㎡まで50%減額といった具合に、一定面積まで評価額を圧縮できます。実際に、小規模宅地等の特例を使うと土地評価額が最大で8割減になるため、相続税額が大きく下がります。例えば、被相続人の自宅土地(評価額8,000万円・面積400㎡)では、特例適用後の評価額は約2,720万円と3分の1以下に圧縮できたケースがあります。賃貸物件を所有していた場合も、要件を満たせば貸付事業用宅地として50%評価減の対象になります。
具体例:高齢の親が老朽化したアパートを所有している場合を考えてみましょう。
親の生前にそのアパートを建て替えて新築の賃貸マンションとし、引き続き賃貸経営を行えば、建物の評価額は固定資産税評価額ベース(新築時の建築費の約60%)となります。加えて、賃貸中であれば貸家建付地・貸家の評価減(土地▲20%、建物▲30%)が適用され、結果として建替え後の不動産の評価額は、建築費や市場価格に比べて実質的に半分以下に抑えられる可能性があります。ただし、新築によって賃貸収入が向上し相続後の収益性は上がりますが、その分相続財産そのものの実質価値が増えるわけではありません。相続税評価額を下げる効果ばかりに目を奪われず、後述のような収支バランスにも注意が必要です。
借入金を利用した節税策の考え方
相続税の計算では、被相続人に債務(借入金)があれば遺産総額から差し引くことができます。そのため、「借金をすると相続税対策になる」と言われることがありますが、単純に借入をするだけでは効果はありません。重要なのは、借りたお金で何をするかです。一般には、借入金を活用して前述の不動産取得や生命保険加入を行うことで、相続税評価額を下げる効果を狙います。ここでは、あえて借入をして純資産を圧縮する方法のメリット・デメリットと、借入に伴うリスク・留意点を解説します。
あえて借入をして純資産を圧縮する方法のメリット・デメリット
借入金を利用して相続税対策を行う代表的な方法が、借入をして賃貸不動産を取得・建設するというものです。自己資金が不足していても借入を活用すれば不動産への資産組み換えが可能となり、結果として相続税の課税評価額を引き下げられます。前述の通り、1億円の借入で賃貸アパートを新築すれば、資産価値は時価1億円でも相続税評価額は約4,200万円に圧縮され、正味の課税対象額が大幅に減少します。その上、建物は家賃収入を生む資産でもあるため、相続後も継続的な収益源となるメリットがあります。借入を活用することで手元資金が乏しくても大きな節税策を実行できる点も利点です。
しかし、借入をしただけでは資産と負債が同額増えるだけで純資産は変わりません。むしろ借入によって利息負担が生じますが、利息の支払いは単に手持ち財産を減らすだけなので、相続税の節税策とはいえない側面もあります。つまり、借入を使った節税は「借りた資金で何をするか」が肝心で、適切に運用しないと効果がありません。不動産投資には空室リスクや維持費も伴いますから、借入金利と賃料収入のバランスが取れないと収支が悪化して資産を減らしてしまう可能性もあります。たとえば賃貸経営が赤字になれば本末転倒で、税負担は減っても肝心の財産自体が目減りしてしまいます。このように、借入を利用した対策には慎重な収支計画が不可欠です。
具体例:自宅に隣接する遊休地を持つ親が、相続税対策としてアパートローンを借り入れて賃貸アパートを建てたケースを考えます。
メリットとして、その土地は更地から貸家建付地となり評価額が低下、建物も固定資産税評価額で算定されるうえ貸家評価減が適用されます。さらに、仮にローン残高が1億円残っていれば、その債務は相続財産から控除されます。結果的に、相続税の課税価格は大幅に圧縮されるでしょう。一方デメリットとして、毎月のローン返済(元本と利息)を賃料収入で賄えるか慎重にシミュレーションする必要があります。空室が増えたり家賃相場が下落したりすれば持ち出しが発生し、せっかく節税しても生活資金が圧迫されかねません。この親御さんの場合も、入居需要の見込みや返済計画を綿密に立てずに計画を進めていたら危険でした。実際には専門家と相談のうえ収支シミュレーションを行い、返済期間中も十分な手取り収入が残る範囲で借入額を設定しています。借入を使った節税策はメリットとデメリットの両面を理解し、長期的な見通しをもって実行することが重要です。
過度な借入のリスクと返済計画の重要性
借入による節税策で気を付けなければならないのは、過度な借入はかえって相続人に負担を残すリスクがあるという点です。もし巨額の借金だけが残ってしまえば、相続人は相続放棄を検討せざるを得なくなったり、相続した不動産を手放して借金返済に充てたりする可能性もあります。節税のためとはいえ、残された家族に返済不能な債務を背負わせるようなことは避けなければなりません。
また、借入で購入した不動産の価値下落や収益悪化にも注意が必要です。例えば、親が築浅の賃貸マンションをローンで取得したものの、地域の賃貸需要が低迷して家賃収入が計画を下回り、ローン返済が重荷になるケースも考えられます。最悪の場合、相続人が物件を売却してローンを完済しても手元に資金が残らない、といった事態にもなりかねません。このような過度な借入のリスクを避けるため、返済計画は保守的に立てることが大切です。金利上昇のリスクや突発的な出費(修繕費の増大など)も織り込んだシミュレーションを行い、「この借入なら最後まで無理なく返せる」という範囲で計画を組みましょう。
なお、相続開始時に借入金が残っていた場合、その債務は相続税の計算上差し引かれますが、生命保険などで債務返済資金を用意しておくことも検討しましょう。例えば親が団体信用保険付きの住宅ローンを利用している場合、親の死亡によりローン残高がゼロになるため相続人に借金を残さずに済みます。同様に、ローン残高と同程度の死亡保険金を受け取れる保険に加入しておけば、相続人は保険金で借入を完済し、資産だけを引き継ぐことも可能です。借入を活用する節税策では、最終的に相続人が困らないための備えもセットで検討しておくことが安心につながります。
二次相続まで見据えた相続税対策
相続税対策を考える際には、一次相続(最初に親の一人が亡くなったとき)だけでなく、配偶者が亡くなった後の二次相続まで踏まえて計画を立てることが重要です。一次相続では配偶者に対する「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」により、配偶者が取得した財産について最大1億6,000万円まで相続税がかからない特例があります。しかし、配偶者に多くの財産を残しすぎると、いざその配偶者が亡くなった二次相続で相続人(子)のみで多額の遺産を相続することになり、結果的に高い税率が適用されて相続税負担が増えてしまうケースが少なくありません。ここでは、一次相続・二次相続をトータルで捉えた相続税対策の考え方を紹介します。
一次相続で配偶者だけでなく子へ分配し税負担を平準化
一次相続では、配偶者に可能な限り多く相続させることでその時点の相続税を大きく減額できます。しかし、「配偶者が相続税ゼロ=最善」とは限りません。配偶者が高齢であれば、その後間もなく発生しうる二次相続で大きな税負担となる恐れがあるためです。
ポイントは、一次相続と二次相続の税負担をトータルで平準化することにあります。具体的には、一次相続の段階で子どもにもある程度の財産を相続させておくことで、配偶者一人に財産が集中するのを避けます。こうすることで、二次相続時の相続財産総額を抑え、高い税率が適用されるのを防ぐ効果が期待できます。
具体例:被相続人の遺産総額が1億円、相続人が配偶者と子1人というケースを考えます。
極端に、一次相続で全財産1億円を配偶者が相続した場合、一次相続では配偶者控除で税はかかりませんが、配偶者死亡時(二次相続)に子が1億円を相続する際には基礎控除3,600万円を超える約6,400万円に課税され、多額の相続税(約1,220万円)が発生し得ます。一方、一次相続で配偶者5,000万円・子5,000万円と法定相続分どおり分割しておけば、一次相続時に子にかかった相続税はごくわずか(数百万円程度)で済み、配偶者死亡時には子が残り5,000万円を相続する形になります。この場合、二次相続時の課税遺産は5,000万円-基礎控除3,600万円=1,400万円程度となり、税額も約160万円で済みます。結果として、二次相続までの総相続税額は約545万円となり、配偶者に全額を相続させた場合(約1,220万円)より半分以下の負担で済んだことになります。このように、一次と二次を通じた最適分割を検討することで、トータルの税額を大きく減らせる場合があるのです。
もちろん、一次相続で配偶者の取得分を減らせば、配偶者の生活資金に不安が生じないかなど慎重な判断が必要です。配偶者控除をフル活用しない場合でも、配偶者の生活保障と税負担軽減のバランスを考え、家族で話し合って決めることが大切です。必要に応じて遺言書で子への遺贈分を指定したり、生前贈与で子に財産を移転しておくことも検討するとよいでしょう。
生命保険の受取人や契約者を調整し二次相続時の非課税枠を確保
二次相続まで見据えた生命保険の活用も有効です。生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)は、一次相続・二次相続それぞれで適用できます。したがって、夫婦それぞれが生命保険に加入しておくことで、一次相続発生時と二次相続発生時の両方で非課税枠を最大限活用することが可能です。
まず、一次相続に備えて受取人を配偶者ではなく子どもに設定しておく方法があります。配偶者はもともと配偶者控除による減税効果がありますが、子どもは生命保険の非課税枠の方が節税効果が大きい場合があります。そのため、被保険者(親)の死亡保険金の受取人が配偶者になっている場合は、事前に子どもに変更することを検討しましょう。例えば父親の保険金受取人を子にしておけば、父親死亡時に子が500万円×法定相続人の数の非課税枠を使えますし、配偶者(母親)の手元に保険金が入らない分、母親の相続財産も増えません。結果的に、一次相続から二次相続までのトータルで見て税負担の軽減につながります。
次に、二次相続に備えて配偶者自身も保険に加入しておく方法です。例えば母親が自分を被保険者とする終身保険に加入し、受取人を子どもにしておけば、母親死亡時(二次相続時)には子どもが再び500万円×法定相続人の数の非課税枠を利用できます。先ほどの例で子どもが2人なら、母親の死亡保険金から最大1,000万円が非課税になる計算です。仮に母親が現金2,000万円をそのまま残して亡くなる場合と、死亡保険2,000万円に加入して亡くなる場合とでは、後者は2,000万円のうち1,500万円が非課税(3人の法定相続人を想定)となり、課税対象がわずか500万円で済みます。預金で残すより生命保険で残した方が相続税が大幅に減るため、夫婦それぞれで保険加入を検討すると良いでしょう。
このように、受取人の設定や契約者・被保険者の組み合わせを工夫することで、一次相続・二次相続それぞれのタイミングで生命保険の非課税枠を最大限活かすことができます。ただし、高齢になってからの保険加入は保険料負担が大きくなる点や、健康状態によっては加入が難しいケースもあります。保険契約は長期の見通しが必要ですので、家族構成や資産状況に応じて早めに検討しておくことが望ましいでしょう。
各種対策を講じる際の注意点
ここまで見てきたように、節税効果のある対策にはそれぞれ伴うリスクやデメリットがあります。相続税対策ばかりに気を取られて本末転倒な結果とならないよう、以下の点に注意しましょう。
節税策に伴うリスク(流動性の低下や維持費用など)
不動産への資産組み換えや賃貸経営による節税策では、資産の流動性低下に注意が必要です。現金は必要なときすぐ使えますが、不動産は売却に時間がかかったり、思うような価格で売れなかったりします。不動産を取得・保有すれば、固定資産税や管理費・修繕費など継続的な維持コストも発生します。また、賃貸物件なら空室リスクや家賃下落リスクが常につきまとうため、計画通りの収入が得られない可能性もあります。たとえば高齢の親が大規模修繕の近い築古アパートを所有している場合、相続税評価は低く済む一方で将来修繕費用の持ち出しが必要になるかもしれません。節税効果と引き換えに資金繰りが悪化したり、資産価値そのものが損なわれては本末転倒です。対策実行前にリスクシナリオを洗い出し、許容範囲かどうか検討しておきましょう。
また、生命保険の活用でも契約内容のチェックが重要です。保険料負担者や受取人の設定によっては、節税どころか思わぬ課税を招く場合があります。たとえば親が子に毎年資金援助し、そのお金で子が親の生命保険料を支払っていたような場合、状況によっては生前贈与とみなされる可能性があります。節税目的で保険契約を変更・新規契約する際は、税務上不自然にならない範囲で行うこと、そして家族にも契約内容を共有しておくことが大切です。
節税対策ばかりに囚われ本末転倒にならないためのバランス
相続税をできるだけ減らしたい気持ちは自然ですが、節税ありきで物事を決めないようにしましょう。大切なのは、残された家族の生活や資産を守ることであり、税金はあくまで考慮事項の一つです。節税策に熱心になるあまり、本来の目的を見失ってしまっては本末転倒です。
例えば、賃貸経営による節税を狙って採算の合わないアパート建築に踏み切れば、確かに相続税評価額は下がるかもしれません。しかし、その結果毎年赤字が続いて資産が減ってしまったら何のための対策か分からなくなってしまいます。また、無理に節税しようとして過大なローンを組めば、返済に苦しんだり家族に負担をかけたりする危険もあります。
対策の効果とリスク、そして家族の将来を冷静に比較衡量し、バランスの取れた選択をすることが重要です。たとえば、「多少相続税は発生しても、親の老後資金は現預金で十分確保しておく」「不動産は節税になるがいざというとき売却しにくいので持ちすぎない」等、節税と資産管理のバランスを考えましょう。子世代として親に助言する場合も、「税金がもったいないから全部対策しよう」と急かすのではなく、親の安心や生活を第一に考えた提案を心がけたいものです。
専門家と十分にシミュレーションする重要性
相続税対策は制度が複雑で、適用要件や効果も人それぞれです。さらに税制改正によって非課税枠や控除額が変わることもあります。したがって、自分たちだけで判断せずに、税理士など専門家のアドバイスを受けながらプランを立てることを強くおすすめします。
専門家に相談すれば、家族構成や資産内容を踏まえたシミュレーションを提示してもらえます。例えば「現状のままだと相続税はいくらになり、どういう対策をすればどれだけ減るか」「一次相続・二次相続のトータルでどの分割プランが有利か」など、具体的な数字で比較検討できます。場合によっては、生命保険や不動産だけでなく、生前贈与(年間110万円の基礎控除枠の活用や住宅取得資金贈与の非課税特例など)を組み合わせた総合的な提案を受けられるでしょう。例えば、子や孫に対して住宅取得資金の贈与を行えば、一定の要件下で最大1,000万円まで贈与税が非課税になる特例があります。この特例を使って親が子に生前に自宅購入資金を援助すれば、相続財産を減らしつつ子世代の住宅取得を支援できます。ただし、この場合は将来の小規模宅地等の特例が使えなくなる(子が自宅を取得すると「家なき子」要件に該当しなくなる)などの影響もあるため、プロの視点でデメリットも含め検討することが重要です。
いずれにせよ、相続税対策は早めの準備とシミュレーションが肝心です。親御さんが健在なうちから、家族でオープンに話し合い、専門家の力も借りながら、自分たちの状況に合った最適な対策を見つけていきましょう。
まとめ(自分の状況に合った相続税対策を選ぶために)
相続税対策には、生命保険の非課税枠の活用、不動産による評価減、借入を活用した資産圧縮、一次二次相続のバランス調整、生前贈与の活用など様々な手法があります。本記事では主な対策の仕組みと注意点を見てきましたが、大切なのはそれらを自分たちの状況に合わせて取捨選択することです。親の資産状況や健康状態、相続人の数や生活状況によって、効果的な対策は異なります。また、節税効果だけでなくリスクやコスト、家族の将来の生活への影響も考慮しなくてはなりません。
50代の子世代の方は、親御さんの意思を尊重しつつ、必要に応じて専門家の力を借りながら、一緒に最適な相続プランを作り上げてください。「税金を減らすこと」自体が目的にならないように注意し、家族の幸せと安心を守るための手段として相続税対策を位置付けることが大切です。早め早めの準備と情報収集で、自分の家庭に合った相続税対策を見つけ、ぜひ実践していきましょう。
最後に、どんな対策を講じる場合でも税制の最新情報を確認し、専門家と十分に相談することを忘れないでください。そうすることで、不安を減らしながら賢く相続に備えることができるでしょう。