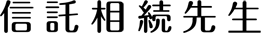相続税対策の基本:早めに知っておきたい生前対策のポイント
- 公開日:
- 更新日:
相続税対策は、高齢の親を持つ50代の子世代にとって、早めに取り組みたい重要なテーマです。相続税の制度は平成27年(2015年)の改正で基礎控除額が大幅に引き下げられ、これにより相続税の課税対象となるケースが増加しました。実際に相続税がかかった方の割合は亡くなられた方全体の約1割(令和5年時点で9.9%程度)に上ります。相続税の課税対象になる遺産規模に達すると、数百万円単位の税負担が生じるため、生前からの対策が欠かせません。そこで本記事では、相続税対策がなぜ必要かという理由から、知っておきたい相続税の基礎知識、生前にできる具体的な節税策の種類、そして対策の第一歩となる資産把握と専門家への相談について解説します。専門的な内容をできるだけ平易にまとめていますので、ぜひ今日からの相続税対策にお役立てください。
相続税対策が必要な理由(早めの準備の重要性)
相続税の課税対象が拡大
かつて相続税は一部の富裕層にだけ関係する税金という印象がありましたが、近年では一般の家庭にも無視できないものとなりつつあります。その背景には相続税の基礎控除額の引き下げがあります。2015年以降、相続税の非課税枠である基礎控除額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に縮小され、例えば相続人が配偶者と子2人(法定相続人3人)なら4,800万円が基礎控除額となりました。このため、自宅不動産や預貯金など合計で4,800万円を超える遺産がある場合には相続税の申告・納税が必要になります。基礎控除額改正前は課税対象となるのは死亡者の数%程度でしたが、現在では約1割が相続税の課税対象となっています。都市部で自宅や土地を所有している家庭や、相続人が少なく基礎控除額が小さいケースでは、特別裕福でなくても相続税が発生し得る状況です。
「生前対策」は時間を味方に
相続税対策を早めに始める最大の理由は、時間をかけることで節税効果を高められる点です。例えば後述する暦年贈与(毎年110万円まで非課税の贈与)による資産移転は、年数をかけてコツコツ行うほど大きな節税効果が得られます。一方で、相続直前になって慌てて贈与しても、被相続人の死亡前3年以内の贈与財産は相続財産に加算され相続税の課税対象になってしまいます(※2024年からはこの持ち戻し期間が死亡前7年以内に延長)。早めに準備を始めれば、この「生前3年(→7年)ルール」の影響を避けつつ計画的に贈与を進めることが可能です。また、親御さんが元気なうちに対策を講じておけば、財産状況の把握や遺産分割の希望について家族で十分に話し合う時間も確保できます。早期からの生前対策は、相続税の節税だけでなく、将来の相続手続きや家族間のトラブル防止にもつながる点で重要と言えるでしょう。
相続税の基礎知識(基礎控除額・税率の仕組み)
相続税がかかる基準
相続税は、遺産総額(プラスの財産から借金や葬式費用を差し引いた正味の遺産額)が一定の非課税枠(基礎控除額)を超えた場合に、その超えた分に対して課税されます。基礎控除額は前述のとおり「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という計算式で求められます。例えば相続人が配偶者と子2人の場合、法定相続人は3人なので基礎控除額は4,800万円です。遺産総額がこの4,800万円以下であれば相続税は一切かかりません。逆に言えば、遺産が基礎控除額を1円でも超えると、その超えた部分に対して相続税の申告・納税義務が生じます。まずはご自身のご家庭の場合、基礎控除額がいくらになるかを把握しておくことが大切です。
税率と課税方法
相続税の税率は一律ではなく、課税対象となる遺産の額に応じた累進課税(段階的な超過累進税率)が適用されます。具体的には、基礎控除後の課税遺産総額をいったん法定相続人ごとに法定相続分で按分し、その各按分額に対して以下の速算表の税率を当てはめて税額を計算します。税率は最低10%から始まり、遺産が大きくなるほど段階的に上昇して、最大で55%(課税遺産総額が6億円超部分)にも達します。例えば課税対象額がそれほど大きくない場合は10~20%程度の税率で済みますが、相当な富裕層のご家庭では半分以上が税金として持っていかれる可能性があるわけです。なお、配偶者が相続する財産については「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」という特例があり、取得した遺産が1億6,000万円まであるいは法定相続分相当額までは相続税がかからない仕組みになっています。配偶者に関するこの特例のおかげで、一般的には夫婦の一方が亡くなった第一次相続では配偶者に多めに遺産を配分すれば相続税を大幅に抑えられる一方、次の節で述べるように二次相続では相続税負担が重くなる点に注意が必要です。
生前にできる主な相続税対策一覧
生前(被相続人が存命中)に講じることのできる相続税対策には、さまざまな方法があります。ここでは代表的な4つの節税対策について、その概要とポイントを解説します。ご家庭の状況に合わせて組み合わせることで、相続税の軽減効果を高めることが可能です。
暦年贈与(毎年110万円非課税の活用)
年間110万円までの贈与非課税枠を使う
生前対策で最も基本的かつ有力なのが「暦年贈与」です。贈与税の仕組みでは、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額が110万円以下であれば贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告も不要)と定められています。この年間110万円の非課税枠(贈与税の基礎控除)を毎年コツコツ活用することで、親の資産を少しずつ子や孫に移転し、将来の相続財産そのものを減らすことができます。例えば親が毎年110万円ずつ子に贈与した場合、10年間で合計1,100万円を無税で移転できる計算になり、相続財産を大きく圧縮できます。受贈者(もらう側)が複数いれば、その人数分だけ毎年110万円枠を活用可能です。例えば配偶者と子2人にそれぞれ毎年110万円ずつ贈与すれば、年間合計330万円を非課税で親族に移すこともできます。
早めに始め長期継続を
暦年贈与の節税効果を最大化するポイントはとにかく早く開始し長期間続けることです。前述の通り、被相続人の死亡前3年以内(※2024年以降の相続では7年以内)の贈与については相続税の計算時に持ち戻し(加算)の対象となってしまいます。そのため、元気なうちから計画的に贈与を行い、「生前○年ルール」の適用を受けない状態で十分な額を移し終えておくことが重要です。なお、毎年同じ時期に同額を贈与し続ける場合には税務署に定期贈与(一括贈与の分割払い)とみなされないよう、贈与契約書を交わす・贈与の都度現金を動かすなど形式面の整備もしておくと安心です(これは専門家に相談するとよいでしょう)。
生命保険の非課税枠活用(法定相続人×500万円の枠)
「500万円×法定相続人」の非課税枠を活用
死亡保険金を活用することも有力な相続税対策です。被相続人が契約者となっている生命保険に加入し、死亡保険金を相続人が受け取ると、その保険金のうち「500万円×法定相続人の数」までは相続税の課税対象から除かれます。この規定を生命保険金の非課税枠と呼びます。例えば相続人が妻と子2人なら、受け取った死亡保険金のうち1,500万円までは非課税で手にすることができる計算です。生命保険金にこのような優遇措置があるのは、受取人が自由に使える現金を速やかに取得できるため、葬儀費用や相続税の納税資金に充てやすいという実情が考慮されているからです。生前対策として、親御さんにある程度の現預金がある場合は、それを死亡保険金という形に置き換えておくことで一定額を非課税で残せるうえ、受取人(相続人)は手続き後すぐに現金を受け取れるというメリットがあります。
活用のポイント
生命保険を使った相続税対策を検討する際は、いくつかポイントに留意しましょう。まず、非課税枠が適用されるのはあくまで法定相続人が受取人となる保険金に限られます。例えば、実際の相続人ではない孫や兄弟姉妹を受取人にした場合、その人は法定相続人ではないため非課税枠は使えず、保険金全額が相続税課税対象になります。また、非課税枠を有効に使うには受取人の人数(=法定相続人の人数)が重要なので、契約時に受取人を複数人(配偶者+子ども等)に設定することも検討します。さらに、保険金は原則として各受取人が受け取った分ごとに非課税枠が適用されますので、契約を複数に分けてそれぞれに非課税枠を充当するという工夫も可能です。生命保険は商品選びや保険料負担の設計も含め複雑な面があるため、保険会社やファイナンシャルプランナーに相談しながら進めるとよいでしょう。
不動産への資産組み換えによる評価額引き下げ
現金より不動産の方が評価が低い
相続税の評価においては、不動産の評価額は現金や預金に比べて低く算定される傾向があります。現金や預貯金は額面どおり100%評価されますが、不動産、とりわけ土地については国税庁が定める「路線価」に基づいて評価します。この路線価は実勢価格(時価)のだいたい80%程度に設定されており、相続税評価額を時価より低めに抑える仕組みになっています。例えば、現金1億円をそのまま持っている場合は評価額も1億円ですが、1億円で土地を購入しておけば相続税評価額上は約8,000万円程度とみなされる、といったイメージです。同じ1億円の財産でも、形を現金から不動産に変えるだけで評価額が下がり、相続税の課税ベースを減らす効果が期待できるのです。
賃貸物件や特例の活用でさらに節税
ただ不動産を取得するだけでなく、賃貸用不動産として活用することで相続税評価額をさらに引き下げることも可能です。例えば親名義でアパートやマンションを購入し第三者に賃貸している場合、その建物は「貸家」、土地は「貸家建付地」として評価され、所有者が自用している不動産よりも低い評価額が適用されます。具体的には、建物については借家人がいることによる一定の評価減(借家権割合による減額、一般に30%)が認められ、土地についても借地権割合に応じた評価減が行われます。その結果、購入価格や時価よりも相続税評価額が大幅に圧縮されるケースも少なくありません。さらに、被相続人の居住用宅地について適用できる小規模宅地等の特例(一定面積まで評価額80%減)など、不動産には税制上の優遇措置が多く用意されています。こうした制度を上手に組み合わせることで、不動産への資産組み換えは相続税対策として大きな威力を発揮します。
注意点
不動産を活用した節税策は効果が大きい反面、流動性の低下や管理コストといったデメリットもあります。不動産は現金のように簡単に分割・換金できず、維持管理や固定資産税の負担も続きます。節税ありきで不動産を購入したものの、相続発生後にかえって遺産分割が難しくなったり、維持できず手放すことになったりしては本末転倒です。資産の組み換えを検討する際は、家族の同意や将来の活用見込み、収支バランスなども含めて慎重に判断しましょう。必要に応じて不動産の専門家や税理士にシミュレーションを依頼し、メリット・デメリットを十分踏まえた上で実行することが大切です。
二次相続まで見据えた遺産分割の工夫
二次相続とは
二次相続とは、夫婦の一方が亡くなった後(第一次相続)に、残された配偶者が亡くなることで発生する2回目の相続のことを指します。例えば父が亡くなった後に母が亡くなるケースが二次相続に当たりますが、この二次相続では一次相続と比べて相続税の負担が増える傾向にあります。主な理由は、基礎控除額と配偶者控除の減少です。二次相続時には配偶者(母)は既に他界しているため相続人の数が減り、その分基礎控除額も小さくなります。また一次相続では配偶者が取得した財産について1億6,000万円まで非課税になる配偶者控除を利用できますが、二次相続ではこの配偶者控除が使えません。その結果、同じ家族内の相続でも一次より二次の方が相続税負担が重くなりやすいのです。実際「第一次相続では相続税がかからなかったのに、二次相続では多額の税金が発生した」という例も珍しくありません。
配偶者に集中させすぎない
上記の理由から、二次相続まで見据えた遺産分割の工夫として重要なのが、「一次相続で配偶者に財産を集中させすぎない」ことです。多くの場合、一次相続では配偶者が存命中であるため、「配偶者にできるだけ多く遺産を相続させておけば相続税が軽減できる(配偶者控除を最大限使える)」「残された配偶者の生活資金を確保したい」といった考えから、配偶者が大半の財産を相続する形になりがちです。しかし前述の通り、その結果として二次相続で基礎控除額の減少や高い累進税率が適用され、一家全体で見れば相続税の総額がかえって増えてしまうことがあり得ます。そこで、一次相続の時点で子ども世代にもある程度の財産を分割して相続させておく方法が検討されます。配偶者控除を適用しても非課税枠を余らせるようなケースでは、あえて一部を子に相続させ少額の相続税を支払っておくことで、二次相続時の課税財産を減らしトータルの税負担を抑えられる可能性があります。具体的には、子に現金や有価証券を分配しておき、配偶者には自宅不動産や生活に必要な資金のみ相続させるといった方法が考えられます。このように一次と二次の税負担をバランスよく平準化することが、二次相続対策のポイントです。ご家族の年齢構成や資産内容によって最適な分け方は異なるため、税理士など専門家と相談しつつシミュレーションすると良いでしょう。
相続税対策の第一歩(資産把握と専門家への相談)
まずは資産の棚卸し
相続税対策を始めるにあたって、現状の資産状況を正確に把握することが第一歩です。親御さん(被相続人になりうる方)の保有する主な資産をリストアップし、その大まかな評価額を算出してみましょう。具体的には、不動産(土地・建物)の評価額(固定資産評価額や路線価などを参考にします)、預貯金残高、有価証券の時価、生命保険の死亡保険金額、借入金など負債の額、といった項目を洗い出します。一見手間に感じますが、現時点で相続税がかかりそうかどうかを判断するには欠かせないプロセスです。国税庁のウェブサイトには**「相続税の申告要否判定コーナー」という簡易計算ツールも公開されており、入力すれば相続税申告の要不要をおおまかに判定できます。こうした公的ツールも活用しながら、まずはご家庭の相続財産見込み額と基礎控除額を比較**してみましょう。
専門家への相談も検討
資産の把握ができたら、その結果に応じて税務の専門家へ相談することも重要です。相続税の計算は複雑で、適用できる特例や控除も多岐にわたります。ご自身だけで対策を進めて見落としがあると、本来払わなくてもよかった税金を余計に支払ったり、逆に申告漏れでペナルティを受けたりするリスクもあります。相続税に詳しい税理士やファイナンシャルプランナーであれば、プロの視点で節税プランを提案し、最適な遺産分割や生前贈与の組み合わせをシミュレーションしてくれます。また最近の税制改正動向(例えば贈与財産の持ち戻し期間延長など)について最新の情報を踏まえたアドバイスを受けられるのも専門家に相談する大きなメリットです。公的機関として税務署の無料相談窓口や国税局電話相談センターなども利用できますが、節税目的の具体的なプランニングまで踏み込んだ助言は難しい場合があります。将来的に相続税が発生しそうな場合は、早めに一度専門家に相談しておくことで、有効な対策の優先順位や今後取るべき行動が明確になるでしょう。相談の際には前述の資産リストを持参すると話がスムーズです。相続は一生に何度も経験することではありません。不安な点はプロに頼ることも検討し、万全の準備を進めてください。
まとめ(今日から始める相続税対策のススメ)
相続税対策の基本と生前にできる主な節税策について見てきました。相続税対策は「とにかく早めに動き始める」ことが肝心です。基礎控除額や税率の仕組みを理解し、自分の家では相続税がかかりそうかを把握したら、今日からできる対策に着手しましょう。毎年110万円までの生前贈与や生命保険の非課税枠の活用、不動産への資産組み換え、二次相続を見据えた遺産分割の工夫など、それぞれの方法には時間をかけることで効果が高まるものばかりです。幸い現時点で相続税の心配がなさそうな場合でも、「備えあれば憂いなし」です。資産の棚卸しや遺言書の検討、家族との話し合いなど、できる準備は進めておくに越したことはありません。また、相続税対策は節税だけが目的ではなく、大切な遺産を次世代に円満に引き継ぐための家族の取り組みでもあります。専門家の力も借りながら計画を練る過程で、家族の将来について話し合う機会にもなるでしょう。思い立った今が一番若い時です。ぜひ本記事をきっかけに、早めの生前対策に踏み出してみてください。