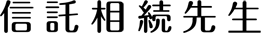家族信託の始め方と手続きの流れ:準備から契約まで徹底解説
- 公開日:
- 更新日:
高齢の親の認知症対策や円滑な資産承継の手段として、「家族信託(民事信託)」への関心が高まっています。しかし、「具体的に何を準備し、どう手続きを進めれば良いのか分からない」という声も多いでしょう。この記事では、高齢の親を持つ50代の方に向けて、家族信託を始めるための準備から契約締結までの流れを専門家目線でやさしく解説します。必要な書類や費用の目安にも触れますので、不安や疑問を解消しながらスムーズに家族信託を進めるための参考にしてください。
家族信託とは、親(委託者)が自分の財産の管理・処分権を信頼できる家族(受託者)に託し、親自身や指定した家族(受益者)のために運用管理してもらう仕組みです。親が認知症になって判断能力を失っても、家族が資産を凍結させず柔軟に管理できるメリットがあります。また遺言代用として、親亡き後の財産承継方法をあらかじめ決めておくことも可能です。以下では、家族信託を始める前の事前準備から契約手続きの流れ、そして必要な費用・書類まで、ステップごとに詳しく見ていきましょう。
家族信託を始める前に準備すべきこと
家族信託をスムーズに始めるには、契約手続きを行う前の入念な準備が欠かせません。ここでは信託前に準備すべきポイントを解説します。
資産・財産の洗い出しと信託計画の明確化
まずは親の保有する資産を整理し、どの財産を信託するか洗い出しましょう。預貯金、不動産、証券など信託に組み入れる財産のリスト(財産目録)を作成します。加えて、家族信託の目的と計画を明確化することが重要です。例えば「認知症による資産凍結を防ぐため」「将来の遺産分割を円満にするため」「障がいのある子の生活を安定支援するため」など、信託を活用する目的を家族で話し合って決めておきます。最初に信託の目的をはっきり決めて共有しておけば、後々の手続きで家族間の揉め事を防ぐことができます。信託期間や受益者(信託で利益を受ける人)、第二受益者(親亡き後に利益を受ける人)など、大まかな信託の設計プランもこの段階で考えておきましょう。
なお、預金や不動産など大半の資産は信託可能ですが、公的年金受給権など一部信託できない財産もあります。専門家に相談しつつ、何を信託財産とするか計画を練ることが大切です。
家族間での話し合いと受託者(託す相手)の選定
家族信託は家族の協力なしには成立しません。親(委託者)と財産を託される子ども等(受託者)だけで決めてしまわず、家族全員で十分に話し合う時間を取りましょう。信託の当事者ではない他の兄弟姉妹にも意向を聞き、不明点を共有しておくことで、後から「聞いていない」といった不満やトラブルを防げます。特に親の財産承継に関わることですから、信託の目的や内容について家族内で透明性をもって合意形成することが円満な信託運用のポイントです。
次に、受託者となる人の選定です。受託者には信託財産の管理処分の大きな権限と責任が委ねられるため、信頼できる人物であることが第一条件です。一般的には子世代の中で親と最も信頼関係が厚く財産管理に適任な人が選ばれます。受託者は親の資産管理を長期にわたり担う役割ですので、金銭管理能力や健康状態、今後のライフプランも考慮して選びましょう。また、受託者が途中で辞任・亡くなった場合に備えて後継受託者を決めておくことも可能です。誰が信託を担うのか家族全員が納得できるよう十分に話し合い、「託す相手」を決定してください。
専門家(司法書士・弁護士)への相談
家族信託の仕組みや契約書の作成には専門的な知識が必要です。自分たちだけで決めようとしても、何をどう定めれば良いか迷うケースは多いでしょう。そのため、早い段階で信託実務に詳しい司法書士や弁護士など専門家に相談することを強くお勧めします。専門家に依頼すれば、家族信託の設計(契約内容の検討)や必要書類の案内、手続き全般についてサポートが受けられます。特に契約書の内容については、登記が可能か(法律上有効か)や税務上問題がないかなど、事前に専門家のチェックを受けると安心です。万一内容に不備があると契約自体が無効になったり、思わぬ贈与税課税を招くリスクもあります。
また銀行で信託専用口座を開設する際、専門家を介さない個人からの申し出だと断られるケースも多いのが実情です。専門家に相談すれば、こうした銀行手続きも含めスムーズに進められるでしょう。最近は初回無料相談を行っている司法書士事務所等もありますので、まずは気軽に相談し、信託設計のアドバイスをもらうのがおすすめです。
家族信託契約の手続きと流れ
準備が整ったら、いよいよ家族信託契約の正式な手続きへ進みます。ここでは信託契約の締結から信託のスタートまでの具体的な流れを解説します。大きなステップとしては、(1)信託契約書の作成, (2)信託契約の公正証書化と信託口口座の開設・財産名義変更, (3)信託開始後の管理・報告という流れになります。
信託契約書の作成(条項の決定と公正証書化)
まず、家族信託の内容を具体化した信託契約書を作成します。前述の家族間の話し合いで決めた内容(信託の目的・信託財産・受託者/受益者・信託の期間や終了条件・財産の帰属先など)に基づいて条項を盛り込みます。契約書の文言はできるだけ具体的にし、あいまいな表現は避けましょう。解釈の余地が残ると後から紛争に発展し、せっかくの信託による財産管理が妨げられる恐れがあります。専門家の協力を得て、「こういう場合はどうするか」「税金面で不利にならないか」等の細部まで検討し、漏れのない契約書に仕上げることが大切です。
信託契約書は当事者間の合意だけでも成立します(私文書でも法律上有効)が、できる限り公正証書で作成することをおすすめします。公正証書とは、公証役場で公証人が作成する公的な契約書面で、高い証明力があります。 特に多くの金融機関が、信託専用の「信託口口座」を開設する条件として契約書の公正証書化を求めています。また公正証書にしておけば原本が公証役場に保管されるため紛失の心配もなく、後日のトラブル防止にも役立ちます。公正証書作成の手続きは次項で説明しますが、専門家と相談しながら必ず公証役場で契約書を作成するくらいの心積もりで準備しましょう。
信託口口座の開設・信託財産の名義変更(登記など)
信託契約書が公正証書で完成したら、実際に財産を受託者へ移し、信託を稼働させる手続きを行います。主に(1)金融財産の管理口座開設、(2)不動産の名義変更(登記)の二つです。
まず金銭や有価証券を信託する場合、受託者名義の「信託口口座」(しんたくぐちこうざ)と呼ばれる専用口座を銀行などで開設します。これは、受託者個人の口座とは別に信託財産を分別管理するための専用口座です。開設時には信託契約書(公正証書)の提出が求められ、銀行によっては事前審査があります。信託金額や契約内容の確認審査を経て承認されないと口座開設できないケースもあり、専門家を通さない個人からの申し込みは断られる銀行も少なくありません。そのため、信託口口座を作る予定がある場合は、契約書作成段階から銀行に相談し審査を進めておくと良いでしょう。無事に口座が開設できたら、親の預金をその信託口口座へ振り替えることで金銭の信託が開始されます。
次に不動産を信託財産とする場合、法務局での信託登記(名義変更)が必要です。親名義の土地や建物を受託者名義に変更し、「この不動産は信託により管理されています」という情報(信託目録)を登記簿に付記します。登記申請にあたっては、委託者(親)と受託者それぞれの印鑑証明書・実印、不動産の権利証(登記識別情報通知)、受託者の住民票、双方の本人確認書類などが必要です。登記の申請は司法書士に依頼するのが一般的ですが、自分で行うことも可能です。その場合、法務局の窓口で事前に相談すると良いでしょう。信託登記を終えると、名義が受託者に変わると同時に登記事項証明書に信託の内容が記録されます。これで不動産も含めた信託財産の受託者への移管が完了し、信託契約が実体的に履行されます。
信託開始後の管理・定期報告の方法
信託契約の手続きが完了し財産の名義が移ったら、家族信託が正式にスタートします。ここからは受託者による財産の管理運用が日常的に行われることになりますが、信託開始後にも守るべきルールと報告義務があります。
まず、受託者は信託財産を自己の財産と明確に区別して管理する義務(分別管理義務)を負います。預かった金銭は信託口口座で管理し、信託用の通帳や帳簿を備えておきます。不動産の場合も、固定資産税や管理費の支払いなど信託財産に関わる収支はできるだけ信託専用の口座経由で行い、公私の財布を混同しないよう注意します。
次に、受託者には定期的な報告義務があります。信託法の定めにより、受託者は少なくとも年に1回、信託財産の収支や残高をまとめた計算書類を作成し、受益者に報告しなければなりません。具体的には、信託財産の貸借対照表(バランスシート)や損益計算書、財産目録、収支報告書といった書類を作成し、受益者(多くの場合は親)に開示します。収益の発生しない自宅不動産の管理などの場合は簡易な収支報告で足りることもありますが、預金や賃貸物件など収益が生じる財産を管理している場合は、毎年きちんと会計報告を行う必要があります。作成した帳簿や報告書類は基本的に10年間の保存義務がありますので、自宅のパソコンで管理表を作る場合もバックアップを取り長期保管しましょう。
なお、家族信託では成年後見制度のように家庭裁判所への定期報告義務はありませんが、その分家族(受益者)への説明責任は受託者に委ねられます。親である受益者や他の家族が安心できるよう、日頃から帳簿を付け領収書類を保管するなど透明性ある管理を心がけることが肝要です。もし不正な管理や使い込みがあれば、受益者は受託者を解任したり損害賠償を請求することも可能ですので、誠実に信託事務を処理しましょう。
家族信託にかかる費用と必要書類
最後に、家族信託を始める際に必要となる費用の目安と準備書類について整理します。費用面は事前に把握して予算計画を立て、書類は早めに集めておくことで手続きが円滑に進みます。
契約書作成費用・登録免許税など費用の目安
家族信託に関連して発生する主な費用項目は以下のとおりです。
信託契約書の公正証書作成費用:
公証役場で信託契約書を公正証書にする際の手数料です。契約内容や信託財産額によって異なりますが、一般的に3~8万円程度が相場ですの設計や契約書作成サポートを専門家に依頼した場合の費用です。一般に信託財産額の1%前後(0.5~1.5%程度)が目安で、最低報酬額が30~50万円程度に設定されているケースもあります。たとえば専門家にフルサポート依頼した場合の総費用相場は50万~100万円程度とされています。一方、信託財産が現金のみ等シンプルなケースでは30~60万円ほどで収まる例もあります。費用は信託の内容や財産規模によって大きく変動しますので、事前に見積もりを依頼すると良いでしょう。
その他の実費:
上記以外にも、契約書用の印紙代(私文書なら200円)や公証役場へ行く交通費、各種証明書の発行手数料(印鑑証明書や戸籍謄本は各数百円)など細かな実費が発生します。ただしこれらは数百~数千円程度と小さいため、主な費用は契約書作成、公正証書化、登記関連と専門家報酬と考えておけば良いでしょう。
費用を抑えるコツとして、自分でできる手続きは自分で行う方法があります。例えば契約書を自力で作成すれば専門家報酬は不要ですし、公正証書にせず私文書契約にすれば公証人手数料も節約できます(その場合でも印紙代200円は必要です)。また、不動産登記も自分で申請すれば司法書士報酬(約10万円)がかかりません。ただし、家族信託は手続きが複雑で内容に不備があるとリスクも大きいため、費用優先で自己流に進めるのは注意が必要です。専門家にポイントだけ相談しつつ一部作業を自分で行うなど、バランスを取りながら進めると安心でしょう。
準備しておくべき書類(財産目録、登記関連書類 等)
家族信託の契約や登記手続きで必要となる書類も事前に揃えておきましょう。主な書類は以下のとおりです。
財産目録(信託財産一覧):
信託の対象とする資産を一覧にした書類です。預金口座の銀行名・口座番号、残高、不動産の所在地・地番、評価額、その他有価証券の内容などをリストアップします。これは契約書の別紙として添付することも多いため、親の持つ全財産を把握してまとめておきましょう。
本人確認書類:
委託者(親)・受託者(子)のそれぞれについて、運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真付きの公的身分証明書のコピーを用意しま。公証役場で公正証書を作成する際や銀行口座開設時に提示が求められます。
印鑑証明書(委託者・受託者):
それぞれの実印について発行後3か月以内の印鑑証明書を取得します。公正証書作成時に公証人へ提出し、登記申請時にも法務局へ提出します。受益者が委託者と別人の場合(例:親が委託者で子が受益者となる特約など)、受益者分も求められるケースがあります。
実印(委託者・受託者):
契約調印や登記申請のためにそれぞれ実印(印鑑証明書と同じ印鑑)を準備します。公証役場での契約署名時や登記書類への押印に使用します。
不動産関連書類(不動産を信託する場合):
対象不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を法務局で取得します。併せて、その不動産の固定資産税評価証明書(市区町村発行)も用意しましょう。これらは契約書作成時や公証人との事前打ち合わせ時に必要となるほか、登録免許税額の算定や登記申請の添付資料として使用します。権利証(登記識別情報通知)も紛失せず手元に用意しておきます。
戸籍謄本:
親子関係など家族関係を証明するために、最新の戸籍謄本(または抄本)を取得します。公正証書作成時に求められる代表的書類の一つです。ケースによっては不要なこともありますが、念のため用意しておくと安心です。
住民票(受託者):
不動産の信託登記では、受託者の住所を証明するために住民票の写しを添付します。発行から3か月以内のものが望ましいです。
以上の書類は、各役所での取得に時間がかかるものもあります。特に戸籍謄本や評価証明書などは早めに請求し、信託契約の手続きをスムーズに進められるよう事前準備しておきましょう。
まとめ(スムーズに家族信託を始めるためのポイント)
家族信託の始め方と手続きの流れを、準備段階から契約後まで順を追って解説しました。最後に、スムーズに家族信託を進めるためのポイントをまとめます。
①早めの準備と目的共有:
親の判断能力がしっかりしているうちに、家族信託の検討を始めましょう。家族全員で信託の目的や必要性を話し合い、合意形成することが第一歩です。目的を明確にしておくことで、手続きの途中で迷いが生じにくくなります。
②信頼できる受託者の選定:
家族信託の中核は受託者です。信頼性はもちろん、財産管理の能力や長期的な責任を担える人物かを考慮して選びましょう。必要に応じて後継受託者の指定も検討してください。
③専門家の活用:
家族信託は万能な制度ではなく、法律・税務の知識も要求されます。無理に自己流で進めるとトラブルになるケースもあります。司法書士や弁護士など専門家への相談・依頼を適切に活用することが、結果的に安心で近道です。
④契約内容の明確化:
信託契約書は将来の道しるべです。条項は具体的かつ平易に記載し、家族が読んでも誤解のない内容にしましょう。後日の争いを避けるためにも専門家のチェックを受け、漏れの無い契約書を作成することが大切です。
⑤計画的な手続き遂行:
公正証書の作成予約、銀行口座の事前審査、登記書類の準備など、各手続きには時間がかかります。スケジュールに余裕をもって進め、必要書類は早めに収集しましょう。事前の準備が万全なら、契約締結から信託開始までスムーズに運びます。
⑥信託開始後の責任ある管理:
信託が始まった後も定期的な報告・帳簿管理を怠らず、透明性を保って運用することが信託成功の鍵です。家族の信頼に応える誠実な姿勢で、信託財産を管理していきましょう。
家族信託は手間や費用もかかりますが、それ以上に**「親の資産を守り、円満に承継する」**ための効果的な手段です。専門家の力を借りながら準備と手続きを踏めば、初めてでも安心して進められます。ぜひ本記事をガイドに、スムーズな家族信託のスタートを切ってください。
本記事は、一般論としてのご案内をしております。対応専門家によって、お手続きの流れや必要資料など、本記事の内容と異なることがございます。具体的な家族信託の実行にあたっては、必ず司法書士・弁護士などの専門家にご相談ください。